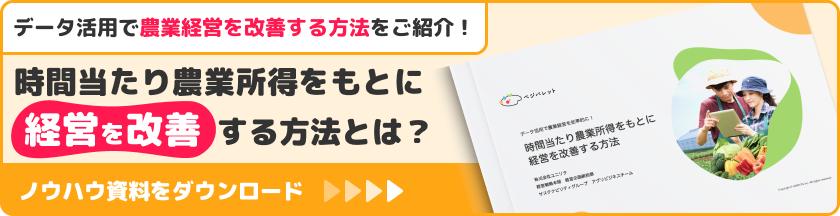トマトの灰色かび病:症状の見分け方と効果的な防除方法
トマト栽培において、「灰色かび病」は農家にとって厄介な病害のひとつです。
本記事では、灰色かび病の症状の見分け方や発生原因を詳しく解説するとともに、防除方法や予防策について具体的にご紹介します。この記事を参考に、トマトを灰色かび病から守り、安定した収穫を目指しましょう。
灰色かび病とは?基礎知識を理解しよう
灰色かび病は、カビ(糸状菌)が原因で発生する病害です。この病原菌は湿気の多い環境で繁殖しやすく、トマトをはじめ、ナスやイチゴなど多くの作物に影響を及ぼします。胞子を飛散して空気伝染するため、特にハウス栽培などの閉鎖空間では、湿度が高い状況が続くことで感染リスクが高まります。
侵入経路としては、農作業や害虫の食害によってできた傷口や枯れた花弁などで、次第に正常な葉や茎、果実などの組織に症状を引き起こします。感染が広がると株全体が枯死する可能性があるため、早期発見と迅速な対応が求められます。灰色かび病を防ぐには、基礎知識を理解し、適切な管理を徹底することが重要です。
灰色かび病が発生しやすい条件
灰色かび病は、湿度や温度などの環境条件によって、その発生しやすさが変わります。また、栽培管理の状況によっても発生リスクが異なります。以下では、灰色かび病が発生しやすい具体的な条件を詳しく解説します。
湿度が高い環境
灰色かび病は湿度の高い環境で繁殖しますが、一説には湿度95%で8~10時間続くと発病するとされています。湿気の多い環境では、盛んに胞子を形成し拡散速度が速まります。特に以下のような状況では、その発生が助長されます。
雨が続く時期
長雨によって土壌や植物表面が常にぬれた状態が続くと、病原菌が繁殖しやすくなります。
過剰な灌水
水やりの頻度や量が多すぎると、土壌や植物周辺の湿度が過剰になり、病原菌が活性化します。
換気不足の温室内
ハウス栽培の場合では、温度管理に重点を置くあまり、換気が不十分になることがあります。これにより湿度が高くなり、灰色かび病の発生リスクを高めてしまうこともあります。
気温が20℃前後
灰色かび病の発育適温は比較的低く15〜25℃です。この温度帯は、春先や秋口の気候条件に一致し、特に次のような時期には注意が必要です。
春先(3〜5月)
日中の気温が上がり始める一方で、夜間は冷え込みが続くため、昼夜の温度差で湿気が発生しやすくなります。
秋口(9〜11月)
日中はまだ暖かさが残るものの、朝晩は涼しくなるため、植物表面や土壌の水分が蒸発しにくく、湿度が上がります。
栽培環境の過密化
植物が密集して栽培すると風通しが悪くなるため、湿気がたまりやすい環境が作られます。これにより、灰色かび病の発生リスクが高まります。特に以下の状況では注意が必要です。
適切な株間が確保されていない場合
株間が狭いと、葉や枝が絡み合い、空気の流れが妨げられます。これにより湿気が逃げにくくなり、菌の繁殖条件が整います。
過繁茂(葉が茂りすぎている状態)
栽培中に適切な摘葉を行わないと、葉が重なり合い、内部が蒸れやすくなります。この状態では、日光が届かず、湿度がさらに高くなるため、病原菌の活動が活発化します。
傷口や枯れた部分
灰色かび病の病原菌は、植物の傷口や枯れた部分を通じて侵入します。以下のような状況では特にリスクが高まります。
枯れた花弁や葉の放置
花が枯れてついたままの花弁や、古くなって枯れた葉は、病原菌が感染する足場となります。これらを取り除かないと、他の部位や株全体に広がる可能性があります。
果実や葉の傷・裂け目
各種の農作業や害虫の食害によって果実や葉に傷がつくと、そこから病原菌が侵入します。
灰色かび病の症状を見分けるポイント
灰色かび病の症状は、主に以下の3つの部位に現れます。
葉の症状
感染した葉には、褐色または灰色の斑点が現れます。進行すると斑点が広がり、葉全体が枯れたり、カビが発生したりすることがあります。
茎の症状
茎の感染部は暗褐色の楕円形病斑を形成し、進行すると茎全体が枯死します。茎が折れたり、病斑が茎を一周したりすると、それより上部の株がしおれます。
果実の症状
果実には灰色のカビが発生し、腐敗します。また、果実表面に白いリング状の病斑(ゴーストスポット)が現れることもあります。
灰色かび病を防ぐ予防策
灰色かび病の発生を未然に防ぐためには、日々の管理が欠かせません。以下は具体的な予防策です。
換気を徹底する
湿気を抑えるため、ハウス内の換気をしっかり行いましょう。窓や換気口を開け、空気の流れをよくすることで湿度を下げることができます。
マルチングを行う
土壌からの病原菌の飛散を防ぐために、マルチングを活用します。黒マルチやシルバーマルチを使用することで、土壌中の植物残渣などに潜む灰色かび病の飛散を抑制することが可能です。また、マルチングは、土壌からの水分の蒸発を防ぐ効果もあるため、特に施設栽培などでは湿度のコントロールにも役立ちます。
花弁や古い葉の除去
受粉後の花弁や枯れた葉をこまめに取り除きましょう。これにより、病原菌の侵入ポイントを減らすことができます。
適切な株間を保つ
適切に間隔を取って苗を植えることで、風通しを改善し、湿気がたまりにくい環境を作ります。
灰色かび病が発生した場合の対処法
灰色かび病を効果的に抑えるためには、防除薬剤を活用することも有効です。以下のポイントを参考にしてください。
ローテーションの実施
同じ薬剤を連続で使用すると、灰色かび病に薬剤耐性を獲得させてしまう可能性があります。薬剤は異なる系統の薬剤をローテーションで使用し、効果を持続させましょう。
散布のタイミングと頻度
発病が確認される前から予防的に薬剤を散布することが効果的です。多湿環境がつづく梅雨の時期や施設栽培などの環境では7〜10日おきに薬剤散布をおこなうのが良いでしょう。
まとめ:日々の管理がトマトを守る鍵
灰色かび病は、湿気の多い環境下で発生しやすく、放置するとトマト栽培に深刻なダメージを与えます。しかし、適切な予防策を実践し、発病後も迅速に対応することで被害を最小限に抑えることが可能です。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。