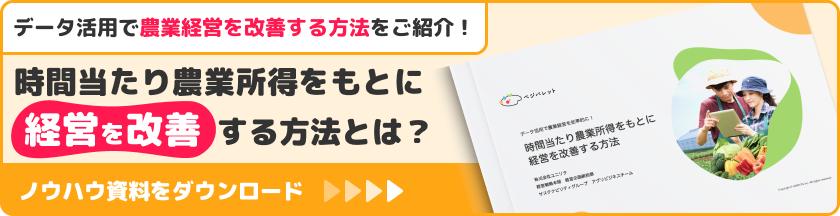キャベツのヨトウムシ被害とは?発生原因と効果的な対策
キャベツ栽培において深刻な被害をもたらす害虫の一つが「ヨトウムシ」です。
本記事では、キャベツに発生するヨトウムシ類の生態や被害の特徴を詳しく解説し、効果的な防除方法を紹介します。農薬を活用した駆除方法だけでなく、天敵の活用や環境整備による予防策など、初心者の方でも実践しやすい対策を幅広く取り上げます。大切なキャベツを守るために、ぜひ本記事を参考にしてください。
ヨトウムシ類とは?生態と特徴
ヨトウムシ類の基本的な生態
ヨトウムシ類は、チョウ目ヤガ科のガの仲間で、野菜や花、果樹などの多くの作物に被害をもたらす害虫です。その名前は、夜間に作物を食害する様子が「夜盗(夜に盗む)」に似ていることからきています。日中は土の中や葉の裏に隠れ、夜になると活動して葉を食害します。ヨトウムシ類は、類似した多くの種類の存在が知られていますが、キャベツの栽培で問題になるのは主に以下の3種類です。
- ハスモンヨトウ
- シロイチモジヨトウ
- ヨトウガ
雌1頭が生涯に産卵する数は平均1,000粒(種類によっても異なります。多いものでは2,000~3,000粒)。産卵1回あたり数十~数百粒の卵塊を産み落とします。幼虫は成長すると次第に散って活動しますが、卵からふ化した幼虫は集団で加害するため、卵を産み付けられた場合の被害は甚大です。
ヨトウムシ類によるキャベツの被害
葉の食害による生育不良
ヨトウムシ類は葉をかじり取るため、キャベツの光合成能力が低下し、生育不良を引き起こします。また、傷口から病原菌が侵入して病気にかかる(二次感染を引き起こす)こともあります。
食害が進行した際の収量・品質低下
幼虫が成長するにつれて食害の範囲が広がり、結球する前の葉が大きく損傷することがあります。葉の損失が激しいと結球不良を引き起こし、収穫量が減少するだけでなく、商品価値が下がる原因となります。
被害の見分け方と初期症状
ヨトウムシ類の被害の初期症状として、葉の表面が不規則にかじられていたり、小さな穴が点在したりしていることがあります。葉の裏側をよく確認すると、卵塊や小さな幼虫が見つかることがあるため、早期発見が重要です。
ヨトウムシ類の発生時期・注意すべき環境
ヨトウムシ類が発生しやすい条件
種類によっても差がありますが、蛹(さなぎ)の状態で越冬していた個体が、温暖になる春から初夏に成虫になり、羽化して飛散、産卵することでヨトウムシが発生します。ハウスなどの施設環境を除く露地では、ヨトウガは年2回、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウは年5~6回発生します(産卵~成虫になるサイクルを繰り返して増殖する)。特に、夏、高温で乾燥していると発生しやすい傾向があると言われています。
発生リスクを高める要因(密植・雑草放置)
ヨトウムシ類の発生を助長する要因として、圃場の管理不足が挙げられます。例えば、雑草が生い茂るとヨトウムシ類の隠れ場所が増え、被害が拡大する可能性が高まります。また、密植状態では風通しが悪くなって隠れる場所も増え、その結果、繁殖しやすい環境になります。
ヨトウムシ類を防ぐ方法
ヨトウムシ類の被害を未然に防ぐためには、物理的対策・生物的対策・環境管理の3つの方法を組み合わせて対策を行うことが重要です。
防虫ネットや寒冷紗を活用する
ヨトウムシ類の成虫(ガ)がキャベツの葉に卵を産み付けるのを防ぐためには、防虫ネットや寒冷紗を設置するのが効果的です。目の細かい防虫ネット(目合い1mm以下)を使用することで、ヨトウムシの侵入を防ぎやすくなります。また、ネットの裾をしっかり固定し、すき間を作らないことがポイントです。
天敵を活用する
生物的防除として、ヨトウムシ類を捕食する天敵を活用する方法もあります。寄生蜂の仲間にはヨトウムシ類の幼虫に卵を産み付けて、ふ化した寄生蜂の幼虫がヨトウムシ類を捕食するものもいます。また、野鳥やカエル、クモなどもヨトウムシ類を捕食します。これらの天敵生物を生かすためには、過度な農薬散布(殺虫剤の使用)を避けて必要最小限の防除にとどめることが必要で、天敵生物が生き残りやすい環境にすることが重要です。
コンパニオンプランツ(忌避植物)を活用する
コンパニオンプランツとは、特定の植物を一緒に栽培することで害虫を寄せ付けにくくする方法です。例えば、マリーゴールドなどをキャベツの周囲に植えると、ヨトウムシ類を忌避する効果が期待できます。
土壌管理と適切な耕作による予防策
ヨトウムシ類は土の中で蛹(さなぎ)になって過ごし、羽化して成虫となったガが産卵することで発生します。そのため、耕起(土を耕すこと)をこまめに行って地表に出してやることで鳥や天敵に捕食させることが可能です。また、マルチング(黒マルチ・シルバーマルチ)を活用することで、ガが飛散するのを防ぐことができます。
ヨトウムシ類の駆除方法
ヨトウムシ類の発生を確認した場合、早期の駆除が重要です。以下の方法を適切に組み合わせて対応しましょう。
物理的対策
ヨトウムシ類を効果的に駆除するには、ふ化前の卵の駆除が非常に重要です。ヨトウムシ類は葉裏に卵を産み付けるため、早期に卵を発見して除去することで、幼虫の発生を防ぐことができます。また、ふ化した幼虫が食害し始めた証しである白っぽい透かし状の葉を見つけたら、幼虫の集団ごと葉を切り取って処分するのも効果的です。成長した個体が潜んでいる場合もあるため、卵が産み付けられた葉を探すのと同時に、葉裏に潜む幼虫を見つけて捕殺しましょう。
化学的防除
農薬散布による化学的防除も、若齢幼虫の時期での使用が効果的です。老齢幼虫になると薬剤への感受性が低下するばかりか、葉裏や土中に潜んで農薬の影響を受けにくくなります。
なお、同じ農薬の連続した使用は、ヨトウムシ類に耐性を獲得させて効果が薄れることにつながるため、異なる有効成分の農薬をローテーションで使用することが推奨されます。
まとめ
キャベツ栽培においてヨトウムシ類は深刻な被害をもたらす害虫ですが、早期発見と適切な防除対策を行うことで被害を最小限に抑えることが可能です。防虫ネットや天敵の活用、環境整備といった予防策を実践しつつ、発生した場合は物理的・化学的防除を組み合わせて対応しましょう。
大切なキャベツを守るために、日々の観察と適切な管理を心がけ、ヨトウムシ類の被害を未然に防ぎましょう。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。