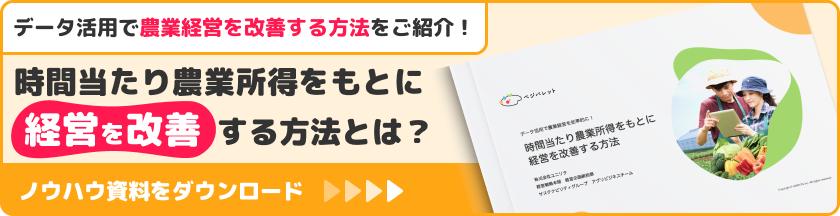キャベツ黒腐病の症状と防除対策|原因と予防法を解説
「黒腐病」は、キャベツ生産農家にとって深刻な被害をもたらす病害の一つです。
この記事では、キャベツ黒腐病の症状、原因、発生しやすい条件を解説し、具体的な防除方法や適切な農薬の選び方について詳しくご紹介します。
キャベツ黒腐病とは?
キャベツ黒腐病の症状
黒腐病は、キサントモナス属の細菌によって引き起こされる病害で、キャベツの他、ハクサイ、ダイコン、ブロッコリーなどを侵します。
キャベツでは、葉脈に沿ってV字型の黄褐色の病斑ができることが特徴です。進行すると病斑内の葉脈は変色して、葉は乾燥して破れ、最終的には枯死します。
病原菌の特徴と伝染経路
黒腐病の病原となる細菌は、種子伝染(黒腐病の細菌に侵された種をまくことで、発芽時に子葉から感染)と土壌伝染(雨などで土壌中の病原細菌が土と跳ね上がって、野菜に付着して感染)によって感染します。また、キャベツの葉などに病斑を作った病原菌は風雨によって飛散します(二次伝染)。
発生しやすい条件とリスク要因
黒腐病は、5~6月あるいは9~10月の比較的気温が低い時期に降雨が続くと発生し、被害が拡大します。
また、感染した種子をまくと発芽時に病原菌がキャベツの幼苗に侵入するため、健全な種子の選定が重要です。水滴や泥によって葉に付着した黒腐病の病原菌は、害虫(モンシロチョウやコナガなど)の食害痕から侵入するため、害虫にも注意が必要です。
キャベツ黒腐病と似た病害の見分け方
黒腐病と類似した病害も多く、見分けることが重要です。
黒斑病との違い
黒斑病は、黒腐病とは異なり、葉全体に黒い円形の病斑が点々と現れます。一方、黒腐病の病斑は葉の縁の方からV字型に現れることが多く、葉脈に沿って広がるのが特徴です。
黒すす病との違い
黒すす病もキャベツをはじめとするアブラナ科作物に発生する病害ですが、黒すす病は夏季の高温多湿の環境で多発する一方、黒腐れ病は5~6月または9~10月の比較的気温が低い時期(黒すす病よりも気温が低い時期)に発生します。また、黒すす病は、黒斑病のような黒っぽい輪紋が初期に発生しますが、黒腐病では葉の葉脈に沿って病斑が現れます。
べと病との違い
べと病では、葉の裏側に灰白色のカビが発生し、表面には黄色っぽい病斑が現れます。
【耕種的防除】キャベツ黒腐病を防ぐ4つのポイント
圃場の環境を整える
黒腐病を防ぐためには、水はけの良い圃場作りが重要です。排水性の悪い土壌では病原菌が繁殖しやすいため、適切な畝立てを行い、排水対策を施すことが効果的です。また、株間を適切に確保して風通しをよくすることで、病気の発生リスクを抑えられます。万が一、感染した株が見つかった場合は、速やかに圃場外へ除去し、被害の拡大を防ぐことが重要です。
種子・苗の適切な消毒と健全な苗の育成
種子に病原菌が付着していると、発芽と同時に病気が広がる可能性があります。そのため、温湯浸漬や乾熱処理による種子消毒を実施し、種子の殺菌処理を行うことが推奨されます。また、健全な苗を選定して、病害に強い個体を育苗段階から徹底的に管理することが、発病の抑制につながります。
害虫の侵入防止と物理的防除の活用
黒腐病の病原菌は、モンシロチョウやコナガ、キスジノミハムシ、コオロギといった害虫の食害痕から侵入します。これを防ぐために、防虫ネットを設置し、害虫の侵入を抑制するのが有効です。また、化学農薬のみに頼らず、天敵昆虫を活用することで、害虫の発生を抑える環境づくりも重要です。
連作障害を防ぐための輪作・抵抗性品種の導入
連作を続けると土壌中の病原菌密度が高まり、黒腐病の発生リスクが増加します。そのため、輪作を行うことで、土壌の病害リスクを低減できます。また、耐病性品種を選ぶことも効果的な対策の一つです。
キャベツ黒腐病に効果的な農薬の種類と使い方
予防的な農薬の使用と適期散布
黒腐病の予防には、銅剤(ボルドー液)が効果的とされています。定植直後から定期的に散布することで、病原菌の侵入を抑えることが可能です。特に台風など風を伴う降雨が予想される時や、管理作業の後など(管理作業によって病原菌が侵入する傷口を作ってしまうため)、銅剤などを散布して予防に努めましょう。
まとめ
キャベツ黒腐病は、感染が広がると収穫量や品質に大きな影響を与えます。防除には、環境管理・農薬の適切な使用・抵抗性品種の導入などが重要です。特に、農業を始めたばかりの方は、病害の発生メカニズムを理解し、早めの対策を徹底することが求められます。キャベツの健全な生育のために、今回紹介した防除方法をぜひ実践してみてください。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。