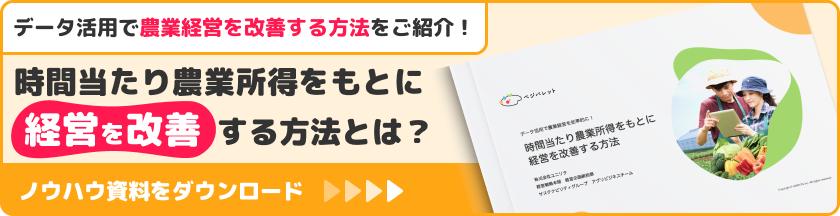トマトのアザミウマ対策:発生原因から防除・予防法まで徹底解説
トマト栽培において「アザミウマ」は、小さな体ながら大きな被害をもたらす厄介な害虫です。
本記事では、アザミウマの生態や被害の見分け方から、具体的な防除・予防法までを詳しく解説します。トマトを守り、安定した収穫を実現するために、ぜひ参考にしてください。
アザミウマとは?基礎知識を知ろう
アザミウマは体長1〜2mmほどの非常に小さな害虫で、植物の葉や果実に被害をもたらします。この害虫は吸汁性で、植物の栄養を吸い取ることで成長を妨げ、果実に傷や変色を引き起こします。また、一部のアザミウマはウイルス病を媒介するため、トマト栽培において特に注意が必要です。
トマトに加害するアザミウマの種類
アザミウマ類は、海外から侵入した種も含めて種類が非常に多く、さまざまな作物に危害を与えます。トマト栽培において特に注意が必要なのは下記の2種類です。
- ミカンキイロアザミウマ
- ヒラズハナアザミウマ
アザミウマが発生しやすい条件
気温と低湿度
アザミウマは20〜25℃の気温を好み、乾燥した環境で特に繁殖が活発になります。露地栽培では、気候の温暖な春から秋にかけての季節に多く発生しますが、施設栽培では冬場も加温により温暖な環境になるため注意が必要です。
雑草の放置
圃場やその周辺に雑草が多いと、アザミウマの隠れ場所や産卵場所となります。雑草を放置すると発生源を増やすことになってしまいます。
アザミウマの被害を見分けるポイント
アザミウマは非常に小さな害虫ですが、その被害はトマト栽培全体に大きな影響を及ぼします。
葉への被害
アザミウマの吸汁による最初の被害は、主に葉に現れます。害虫が葉の表面から栄養を吸い取ることで、小さな斑点や傷が生じます。これらの症状は一見すると見落としがちですが、次第に以下のような特徴が現れてきます。
斑点や変色の出現
吸汁された箇所が変色し、黄色や褐色の小さな斑点として目立つようになります。この変色は特に葉の表面に集中し、葉全体が不健康な見た目になります。
葉の縮れや変形
新芽部分が加害されると、新葉が正常に展開しなかったり、縮れて湾曲したり、奇形になって現れたりします。
枯れの進行
被害がさらに拡大すると、完全に枯れてしまい、株全体の光合成能力が低下します。これが原因で植物の成長が大きく阻害されます。
果実への被害
アザミウマは果実にも直接的な被害を与えます。果実表面への傷だけでなく、見た目や品質に深刻な影響を及ぼします。
果実の変色・斑点
アザミウマの成虫は果実の子房に産卵するため、成熟前の幼果では、特に産卵痕(円形に白く膨れ上がった「白ぶくれ症状」)を残します。「白ぶくれ症状」は、果実の成熟に伴って目立ちにくくはなりますが、どうしても消えないため商品価値を損ないます。また、吸汁された果実では、その部分が褐色に変色して(またはかさぶた状になって)残ります。これにより、果実全体の外観が損なわれ、商品価値が低下します。ミニトマト、中玉トマトでは、アザミウマが吸汁した際に、果実表面に金色の微小な斑点を残して、金粉が降りかかったような外観になってしまいます。
株全体への影響
アザミウマの被害は葉や果実だけにとどまらず、株全体の健康状態にも深刻な影響を及ぼします。
ウイルス病の媒介による二次被害
アザミウマはウイルス病(トマト黄化えそウイルス)を媒介することがあり、これに感染するとトマト株全身がえそ症状を引き起こして被害がさらに深刻化します。ウイルス病は一度感染すると治療が難しく、株全体に広がるリスクがあります。
収穫量の減少
葉や果実への被害が進行すると、株全体の生育が悪化し、結果として収穫量が減少します。さらに、被害を受けた果実は品質が低下するため、出荷可能な果実の数も減ってしまいます。
アザミウマを防ぐ予防策
防虫ネットの設置
物理的に害虫の侵入を防ぐには、防虫ネットが有効です。目の細かいネットを使用することで、アザミウマだけでなく他の小型害虫も防ぐことが可能です。施設栽培では、天窓・出入り口などに0.4mm程度の目合いの防虫ネットを利用することで侵入防止に期待ができます。防虫ネットの目合いが小さい方が侵入を防ぐことができますが、通気性が低下するため注意が必要です。また、赤色の防虫ネットを利用すると高い忌避効果が期待できるため、0.8mm程度の目合いのネットでも侵入抑制効果があると言われています。
シルバーマルチの活用
シルバーマルチは、地面からの反射光で害虫の飛来を抑制する効果があります。アブラムシ類などの害虫のほか、アザミウマ類も例に漏れず、シルバーマルチを張ることで、忌避効果が期待できます。
雑草の除去
定期的に雑草を除去し、アザミウマの産卵場所をなくします。周辺に繁殖地となる雑草の無い環境を維持することは、長期的な予防につながります。
適切な施肥管理と生育
窒素過剰による軟弱生育などではアザミウマ等の害虫被害に負けてしまいます。適切な施肥管理を心掛け、しっかりした草姿・草勢を作り上げることも大切です。
アザミウマの駆除方法
粘着シートの設置
アザミウマは黄色や青色に集まる性質があるため、これらの色の粘着シートを圃場に設置することで捕獲可能です。粘着シートは、定期的に交換することで捕虫効果を期待できるばかりか、アザミウマ類の増減の傾向をモニタリングするツールとしても活用できます。
天敵昆虫の活用
アザミウマを捕食する天敵生物を活用することで、自然環境を損なわずに害虫を制御します。トマトに適用のある天敵農薬として製品化されているものでは、スワルスキーカブリダニ、ククメリスカブリダニ、タイリクヒメハナカメムシなどがあります。
農薬散布
初期の発生段階で農薬を散布することで、被害を最小限に抑えます。薬剤の使用は成虫や幼虫の発生時期を見計らって行い、耐性の発生を防ぐために作用機構の異なる薬剤をローテーションで使用します。また、天敵生物を放飼している場合には、天敵生物に影響の少ないものを選んで使用します。
複合的な対策でアザミウマを防ぐ
アザミウマ対策には、防虫ネットやシルバーマルチなどの物理的な手法と、農薬散布や天敵昆虫の活用といった化学的・生物的な手法を組み合わせることが効果的です。また、日々のモニタリングを徹底することで、早期発見と迅速な対応が可能となり、被害の拡大を防ぐことができます。
まとめ
アザミウマの発生を防ぎ、被害を最小限に抑えるためには、発生条件の理解と予防策の実践が重要です。防虫ネットやシルバーマルチ、天敵昆虫の導入、適切な農薬の使用など、複合的な対策を取り入れましょう。日々の観察と環境管理を徹底することで、大切なトマトを守り、高品質で安定した収穫を実現してください。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。