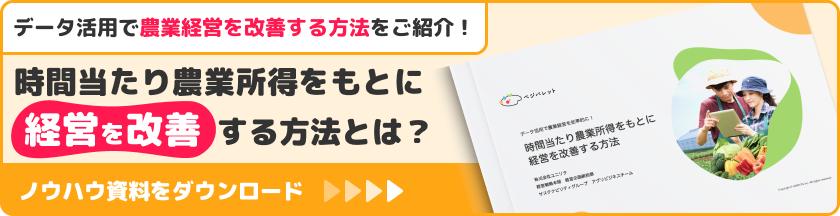トマトの低温障害とは?原因と防止対策を解説
露地栽培、施設栽培問わず一年を通して生産されるトマトの栽培において、生産者が直面する課題の一つに「低温障害」があります。
この記事では、低温障害の発生する状況や主な症状、防止対策、障害が発生した場合の対処法を解説します。
トマトの低温障害とは
低温障害とは、作物が生育適温を下回る環境にさらされることで、正常な生育が妨げられる現象です。トマトの生育適温は、昼間20~25℃、夜間15~18℃程度とされています。この温度を大きく下回ると、新陳代謝が鈍り、葉や果実に異常が発生する場合があります。
また、低温障害は「一時的な気温の低下」でも発生する可能性があるため、気温の変化を注意深く把握する必要があります。
トマトの低温障害の主な症状
トマトが低温障害を受けると、以下のような症状が見られることがあります。
葉や茎の変色
軽度の低温障害では、葉にアントシアニンが生成されて紫色に変色する程度ですが、さらに進むと、葉や茎が斑点状に茶色く変色したのち白化し、ダメージを受けた組織から枯れていきます。
果実の生育不良と奇形
果実が正常に膨らまず、小さいまま成熟したり、閉じたファスナーのような傷が表面についたチャック果や、窓あき果(果実表面の一部が窓を開けたように陥没)、さらにはやけどが治ったようなあとが残るケロイド症果と言った奇形果になったりします。
花落ち
開花期に低温環境が続くと、花が十分に育たず、落花することがあります。これにより、収穫量が大きく減少するリスクが高まります。
根の成長停滞
生育適温を下回るような低温では、肥料や水の吸収という根の機能が低下します。また根自体の損傷も起こり、土中で湿った冷たい土に触れている場合は根腐れなどが発生するため、養分、水分の吸収が阻害されます。
これらの症状を放置すると、収穫量だけでなくトマトの品質全体に悪影響を及ぼすため、早期発見と対策が重要です。
トマトの低温障害の原因
低温障害の原因には、気象条件だけでなく、以下のような栽培環境や管理の不備も含まれます。
不十分な管理
簡易的なビニールハウスやトンネル栽培では、夜間の冷気を完全に遮断できないことがあります。また、ハウス内の出入り口付近などの温度ムラが原因となって、トマトが低温にさらされるリスクが高まります。
地温の低下
トマトの根は地温にも敏感です。地面が冷えると根の吸水能力が低下し、栄養の吸収が妨げられます。地温を保つためのマルチングや寒冷紗による保温は重要です。一方、かん水時の水温が低すぎる場合も、低温障害を引き起こす要因になります。
トマトの低温障害の防止対策
低温障害を防ぐために、以下のような対策が有効です。
1. ビニールハウスや温室の活用
ビニールハウスや温室設備は、トマトを低温障害から守るための効果的な手段の一つです。これらの設備は外気温が低い時期でも内部の温度を安定させる役割を果たします。
被覆資材の利用
ビニールハウスの外張り被覆資材としては、さまざまな素材がありますが、結露の起こりにくい素材を選ぶことで病気の発生の程度も異なります。被覆資材を二重、もしくは三重にして使用することで断熱性が向上し、冷気を遮断できます。
夜間の保温対策
夜間は特に温度が下がりやすいため、内部に保温カーテンや暖房機を設置するのも有効です。これにより、夜間の冷え込みによるストレスを軽減できます。
2. 地温の維持と有効活用
効果的なマルチング
地温を安定させるために効果的なのがマルチング(地面を覆う資材の活用)です。マルチングは土壌の温度を一定に保つだけでなく、雑草の抑制や水分の蒸発防止にも役立ちます。
黒色または透明フィルムを使用して地温を保ち、さらに稲わらで断熱効果を高めることも有効です。
3. 温度管理に役立つ技術やツールの活用
近年では、温度管理に役立つさまざまな技術やツールが開発されています。これらを活用することで、低温障害を回避することが可能です。
温度センサーとデータ管理
温度センサーを使用すると、ビニールハウス内の温度もしくは栽培圃場の外気温をリアルタイムでモニタリングできます。スマートフォンやPCと連携させることで、遠隔地からでも温度状況を確認することが可能です。施設栽培であれば、外気温に応じて暖房設備や換気設備を操作することが可能です。
複合環境制御
ハウス内の温度や湿度、二酸化炭素濃度を自動で調整するシステムを導入することで、細かい管理が不要で温度管理ができ、かつ植物の光合成能力の上昇、ひいては収量の向上が見込めます。このようなシステムは初期投資が必要ですが、安定した収穫量と品質の向上が期待できるため、中長期的に想定した以上の費用対効果が得られる可能性があります。
トマトの低温障害を防止するには、設備投資と適切な技術の活用が不可欠です。設備投資は初期費用が負担になるかもしれませんが、長期的な収量や品質を考慮すると、それだけの価値が見込めます。
トマトの低温障害への対処法
低温障害が発生した場合、以下の応急処置が役立ちます。
急激な温度上昇を避ける
低温障害が発生したトマトに対して、ハウス内や周囲の温度を急激に上げるのは避けてください。温度を急激に上げると、植物がさらなるストレスを受け、回復が遅れる可能性があります。ハウス内の温度を徐々に上昇させるように注意しましょう。
葉面散布による栄養補給
低温障害を受けたトマトは栄養吸収が不十分になりがちです。即効性のある葉面散布肥料を使用することで、葉から直接栄養を補給し、トマトの弱った生育を助けてやることが可能です。葉面散布の際は、植物に優しい濃度であることを確認し、日差しの強い時間帯を避けて行うのがポイントです。
被害を受けた葉や果実の切除
低温障害で枯れてしまった葉や果実は、株全体への栄養の流れを阻害することがあります。光合成のために必要な新葉が展開していることを確認しつつ、被害がひどい部分は切除して、株のエネルギーを健康な部分に集中させるようにしましょう。
地温の回復
低温障害が発生した場合、地温の低下による影響も少なくありません。地温を回復させるためには、マルチングや稲わらを活用して土壌を効果的に保温しましょう。
まとめ
トマトの低温障害は、各地域で年間通して、さまざまな作型で栽培されるトマトの生産において、避けては通れない課題の一つです。この障害は、トマトの収穫量や品質に深刻な影響を及ぼしますが、予防策や対処法を実践することで、そのリスクを軽減することが可能です。
トマトの低温障害に対する理解を深め、計画的に対策を講じることで、安定した収穫と品質を実現することが可能です。温度センサーによる栽培環境のモニタリングツールを活用すれば、効率的な温度管理や生育状況のモニタリングができるため、栽培経験の少ない生産者でもスムーズに課題へ対応できます。
今後も気象条件や栽培技術の進化に合わせて知識をアップデートしながら、より良い農業経営を目指していきましょう。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。