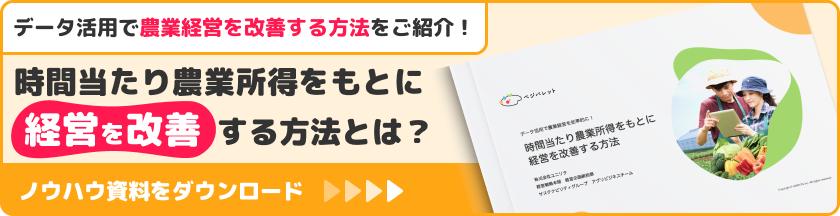トマトの青枯病とは?原因と対策を詳しく解説
トマト栽培において、生産者が直面する課題の一つに「青枯病」があります。この病害は、収穫量の大幅な減少をもたらす恐ろしい病気です。
この記事では、トマトの青枯病に関する基礎知識から、発病を防ぐための効果的な対策までを分かりやすく解説します。初心者でも取り組みやすい実践的なアドバイスを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
トマトの青枯病とは
青枯病は、ラルストニア属に分類される細菌が原因となって発生する植物の病害です。この病害は、トマトなどのナス科作物をはじめ多くの植物に見られ、感染すると急激にしおれ、やがて枯死します。病名の由来は、感染した植物が青々とした状態のまま枯れてしまうことから名付けられています。
青枯病の最大の特徴は、進行が非常に速い点です。感染が確認されてから数日で植物全体が枯れてしまうため、感染後の対応が難しい病害です。また、細菌は土壌や水を介して広がりやすく、圃場全体に被害が拡大するリスクが高いのも特徴です。
トマト栽培における青枯病の被害例
青枯病が発生すると、次のような被害が見られることがあります。
収量の大幅な減少
青枯病に感染した株はしおれてしまうため、その時点で果実の成長は止まってしまいます。そのため、収穫量が大幅に減少します。大規模な発生が確認されると、圃場全体の収量に深刻な影響を与えます。
農業経営への影響
青枯病の被害が深刻化すると、同じ土壌で再び作物を育てることが難しくなることがあります。そのため、土壌改良や圃場管理に追加のコストが必要となり、経営に影響を及ぼします。また、青枯病が発生して、収穫量が例年の50%以下に落ち込んだという事例も聞かれます。このように、病害への十分な知識や対策がない場合、事業継続が困難になるリスクがあるため、青枯病への備えは極めて重要です。
青枯病の青枯病菌の特性
青枯病菌の特性として以下の点が挙げられます。
多様な感染経路
青枯病は、土壌・水・作業器具を介して広がります。例えば、感染土壌で育てられた作物が枯れ、その残骸が分解されることで細菌が土壌中に蓄積します。また、かん水や雨水を通じて圃場内で拡散することもあります。
高い生存能力
青枯病の病原菌は湿った環境や暖かい気候で活発に増殖します。また、土壌中では数年程度生存できます。このため、対策なしには次作での再発リスクが高まります。
青枯病が発生しやすい土壌や気象条件
青枯病の発生リスクが高まる主な条件は以下の通りです。
水はけの悪い土壌
青枯病菌は湿潤な環境を好むため、水はけの悪い土壌で発生リスクが高まります。雨が続いたり、かん水過剰で土壌が過度に湿ったりすると、菌の増殖が促進されます。
高温多湿な気候
青枯病の細菌は気温25~37℃で発病が著しくなります。このため、夏季や梅雨の時期に発生率が上昇します。
未消毒の作業道具
青枯病は、収穫や芽かきなどの農作業による接触伝染でも広がります。消毒されていない作業道具を使用することで、感染が拡大する可能性が高まります。
連作の影響
同じ圃場でトマトを含むナス科作物を繰り返し栽培することで、青枯病菌が土壌中に蓄積し、次の栽培に影響を与えます。連作障害を防ぐためには、土壌消毒や輪作(作物の種類を変える栽培方法)が効果的です。
青枯病と類似症状を持つ病害との見分け方
青枯病は日中の暑い時間帯に葉がしおれ、夜間や涼しい時間帯には一時的に回復することがあるなど、施肥やかん水管理が原因でしおれたものと勘違いすることも少なくありません。青枯病の見分け方については、以下の通りです。
見分け方:根の褐変・維管束の変色
しおれた株を抜いて根が褐色に変色していたり、茎を縦に切ったり、輪切りにして維管束(茎の内部)が茶色または黒っぽく変色していたら青枯れ病が疑われます。また、輪切りにした茎を水に浸して切断面から濁った白い液体がしみ出してきたら青枯れ病と考えて間違いないでしょう。
トマトの青枯病の防止対策
排水対策を含む適切な圃場管理の実践
排水性の向上
水はけが悪い圃場では、青枯病の原因となる病原菌が増殖しやすくなります。畝を高くする「高畝(たかうね)」栽培を取り入れることで、雨や灌漑による過剰な水分が土壌にたまるのを防ぐことができます。
適度な潅水管理
水のやりすぎは土壌の過湿化を引き起こし、病原菌の増殖を助長します。土壌水分の量を定期的に確認し、過剰な潅水を防ぐことが重要です。
土壌改良
土壌の排水性を高めるために、堆肥や腐葉土を混ぜ込むことで通気性と保水性のバランスを整えることができます。
農薬を活用した土壌消毒と消毒方法
土壌消毒の方法
農薬を使った土壌消毒や太陽熱を利用した土壌消毒があります。太陽熱消毒は夏季の強い日差しを利用し、透明なビニールシートを地面に覆って温度を上昇させ、病原菌を死滅させる方法です。一方、青枯病に有効な農薬を使用することで、土壌中の病原菌を効果的に減少させることも可能です。
作業器具の消毒と衛生管理の徹底
作業器具の消毒方法
収穫ハサミや手袋などの道具を使用する際は、次亜塩素酸ナトリウムやエタノールを使用してこまめに消毒を行いましょう。特に、病気に感染した株を取り扱った後は、速やかに消毒を実施してください。
抵抗性品種を利用した接ぎ木栽培の活用
抵抗性品種とは?
青枯病に対する耐性を持つ台木品種を使用することで、感染リスクを低減することができます。ただし、抵抗性品種である台木を用いたとしても、感染を完全に防げるわけではありません。一般的な接木法で行われる双葉の上で接木をするよりも、本葉2~3枚で接木する高接接木法の方が、根から侵入した青枯れ病菌が感染して株がしおれる等の症状が現れるまでの時間を稼げるため、収穫期間を長くさせることができます。
地温管理とマルチングによる予防効果
マルチングの活用
マルチやわらを土壌表面に敷くことで、土壌温度を一定に保ちます。特に、地温が高くなりすぎる夏場には、地表面を覆うことで過剰な熱が作物に影響を与えるのを防ぐ効果もあります。
トマトに青枯病が発生した場合の対処法
感染株の早期除去と適切な処分方法
感染株の迅速な除去
青枯病の症状が確認された株は、速やかに引き抜いてください。この際、根を含めて完全に取り除くことが重要です。感染した部分が残ると、病原菌が土壌に残り、再感染のリスクが高まります。
適切な処分方法
感染株は、圃場外で適切に処分してください。感染株を圃場内で堆肥化すると、病原菌が再び土壌中に拡散する恐れがあります。
周辺の株の観察
感染株を除去した後は、周囲の株を注意深く観察し、同様の症状が現れていないか確認してください。早期発見が被害の拡大を防ぐ鍵となります。
まとめ
トマトの青枯病は、生産者にとって避けて通れない重要な課題です。この病害は、土壌や気候による温度などの条件、栽培環境によって発生リスクが高まり、管理を怠れば収穫量の大幅な減少や品質の低下を招きます。しかし、原因を正確に理解し、予防策や対処法を適切に実施すれば、被害を最小限に抑えることが可能です。
トマト栽培は、適切な知識と準備があれば成功の可能性を広げることができます。青枯病への備えを徹底し、安定した収穫を目指して取り組んでみてください。
この記事が、実践的な栽培管理を始めるための一助となれば幸いです。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。