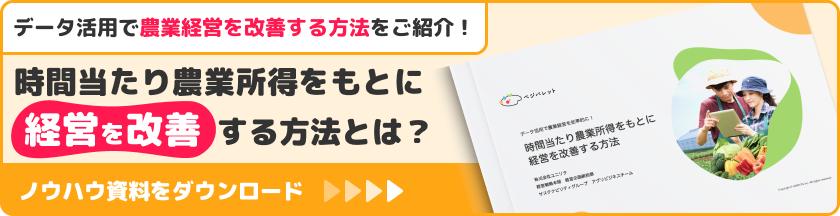トマトのハダニ被害を防ぐ!原因、症状、効果的な駆除・予防
トマト栽培において「ハダニ」の被害は、品質や収量に大きな影響を与える厄介な問題です。
本記事では、新規就農者や若手農家の方にもわかりやすく、トマトのハダニ被害の原因や症状、効果的な駆除・予防方法を解説します。ぜひ、この記事を参考に、ハダニ被害を未然に防ぎ、大切なトマトを健康に育ててください。
ハダニの生態
ハダニはクモの仲間に属する小さな害虫で、トマトを含む多くの農作物に被害を及ぼします。その体長は約0.5mmと非常に小さいため、なんとか肉眼で発見するのができる程度の大きさです。また、葉の裏側に付着して繁殖するため、気付いたときには大きな被害になっていることも珍しくありません。ハダニは温暖で乾燥した環境を好み、暖かい季節になると、その数を急激に増やします。一度発生すると、その繁殖力の高さから被害が拡大しやすく、放置することで収穫量に大きな影響を与える可能性があります。
トマトにおけるハダニ被害
ハダニがトマトに与える影響は主に葉に現れます。ハダニによる被害の初期症状としては、以下になります。
葉の表面に白や黄の斑点が発生
ハダニが栄養を吸い取ることで葉の表面に白や黄色の斑点が生じます。この斑点が広がるとこすれたような色抜け状の見栄えになるばかりか、葉の葉緑素が抜けて光合成に影響を与えます。
葉の裏側にクモの巣状の糸が見られる
ハダニはクモの仲間であるため、寄生している場所に細い糸を張ります。糸が多く見られる場合には、目を凝らして見ると、そこにハダニが大量発生している可能性があります。
葉が徐々に変色し、枯れて落ちる
ハダニの被害が進行すると、葉全体が黄色く変色し、やがて乾燥して枯れ落ちます。植物としてのトマトの健康状態が大きく損なわれ、果実に十分な栄養を届けられなくなります。
定期的に葉の裏側を観察し、白い斑点やクモの巣状の糸を見つけたら早急に対処しましょう。
ハダニが発生しやすい時期と条件
ハダニは暖かい季節に発生しやすく、春から夏にかけて注意が必要です。特に梅雨が明けた後の高温乾燥期には被害が多発します。この時期は、環境条件によって爆発的に繁殖するため、被害を抑えるには重要なタイミングです。
発生しやすい条件
ハダニの発生を引き起こしやすい条件には以下のような要因があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
高温乾燥期の気候
ハダニは湿度が低い環境を非常に好みます。特に梅雨明け後、雨が減少して気温が25~30℃近くになる季節はハダニにとって絶好の繁殖環境です。この時期、ハダニの卵がふ化するには2~3日、繁殖能力のある成虫になるには6~7日です。そのため、10日程度で、次の世代が産卵できるため爆発的に増えていきます。1匹のメスはその生涯で100個以上の卵を産むため、この時期に一度発生すると短期間で被害が広範囲に広がる危険性があります。
密集した栽培環境
風通しの悪い密集した栽培環境は、ハダニの発生リスクを高めます。栽植密度の高い圃場や、込み入ったトマトの枝葉は、ハダニが飛来して移動する上での足場や隠れ家となります。葉が重なり合うことで被害箇所が見えにくくなるため、発見が遅れがちになります。
土壌の水分不足
ハダニの発生は土壌の乾燥とも深い関係があります。水分が不足すると、植物の葉や茎が乾燥しやすくなり、ハダニにとって理想的な寄生環境となります。空気の乾燥と同様に、土壌の乾燥にも注意が必要です。
ハダニの発生を抑えるには、上記の条件を理解し、栽培環境を適切に管理することが予防につながります。
トマトについてしまったハダニの駆除方法
トマトに寄生したハダニを駆除するには、発生状況や規模に応じた方法を選ぶことが重要です。ハダニは乾燥環境を好み、葉の裏側に集まる性質があるため、駆除には物理的な方法や無農薬スプレー、市販の農薬、天敵の活用などを組み合わせて行うと効果的です。
水を使った物理的な駆除
ハダニは水に弱いため、葉にスプレーして散水し洗い流すことが有効です。特に葉の裏側を重点的にぬらすことで、ハダニを物理的に除去できます。また、葉裏の水洗いや圃場全体への散水によって湿度を上げれば、ハダニの活動を抑制する効果も期待できます。環境負荷が少ないため、初期段階の駆除に適しています。
無農薬スプレーの活用
家庭にある食品を用いたスプレーは、環境に優しい駆除方法として人気です。特に酢については、数日おきの定期的な散布によってハダニを忌避させる効果があると言われています。
市販の農薬の使用
農薬を使用する場合は、ラベルをよく確認し、ハダニに適用のある農薬を選ぶ必要があります。ただし、葉に点状から擦れたような色抜けが発生するのは、アザミウマ類も一緒です。異なるのは、葉の裏側に「白っぽくて光沢がある」のがハダニ類。葉の裏側に「光沢はあるものの、黒い微小な汚れがある」のがアザミウマ類です。使用する農薬が異なるため、見分け方が重要になります。農薬は、同じ作用機構(効き方)のものを使い続けるとハダニが薬剤耐性を持つ可能性があるため、異なる農薬をローテーションで使用することが基本です。
天敵の活用
化学農薬を使わずにハダニを抑える方法としては、「ミヤコカブリダニ」や「チリカブリダニ」といった天敵の利用も検討できます。これらの天敵はハダニを捕食し、自然に個体数を減少させる効果があります。天敵を導入する際は、化学農薬の使用を控えるなど、生存しやすい環境を整えることが成功のカギとなります。
ハダニを予防する方法
ハダニの発生を未然に防ぐには、栽培環境の整備や適切な管理が欠かせません。以下の予防策が効果的です。
環境を整える予防策
トマト栽培においては、風通しをよくし、適度な湿度を保つことが予防の基本です。株間を広く取って不要な枝葉を摘除することで、ハダニの足場や隠れ家を作らせない、繁殖しにくい環境にできます。また、夏場の高温期には適時水やりをして圃場の乾燥を防ぐことで、ハダニの活動を抑制することが期待できます。圃場内や圃場周辺の雑草を定期的に除去することで、トマト株に飛来する前の隠れ家や繁殖エリアを減らすことが可能です。
防虫ネットの活用
ハダニの体長は約0.5mmと非常に小さく、一般的には防虫ネットを利用しての侵入防除は難しいとされています。目の細かい0.4mm目合いでは、同じく微小害虫のコナジラミやアザミウマは防げますが、ハダニについては疑わしいところです。最近では、0.25mm目合いの防虫ネットも開発され、ハダニの発生も防げたとする声もあるため、試してみる価値はあるかもしれません。ただし、防虫ネットは通気性が悪くなるため、栽培環境の温度管理に注意が必要です。ハウス栽培では、換気扇やサーキュレーターを併用するのが効果的です。
まとめ
ハダニは小さな害虫ですが、放置するとトマト栽培に深刻な被害をもたらします。早期発見と適切な駆除方法を実践し、栽培環境を適切に管理することで、ハダニの発生を効果的に抑えることができます。
この記事で紹介した方法を参考にしながら、大切なトマトを守るための対策をぜひ実践してください。日々の観察と管理を徹底し、たくさんのトマトの収穫につなげたいものです。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。