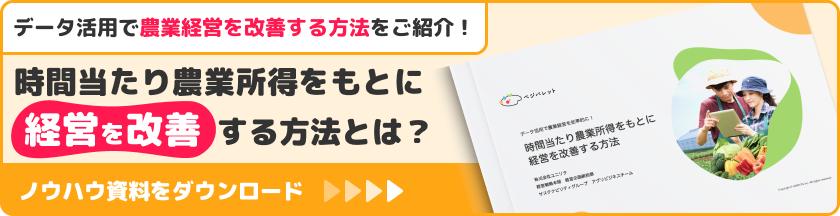キャベツの根こぶ病とは?原因・症状・防除対策を解説
キャベツの「根こぶ病」は、栽培において深刻な問題となる病害の一つです。
この記事では、キャベツの根こぶ病の症状、発生原因、伝染経路を詳しく解説し、効果的な防除対策について紹介します。農業を始めたばかりの方でも実践しやすい管理方法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
診断のポイントは?キャベツ根こぶ病の被害症状
根こぶ病の症状と進行の特徴
根こぶ病は、根にできたこぶが肥大して、根が正常に機能しなくなることで水分や養分を吸収できなくなる病気です。発症する場所が根であるため地上部の生育の様子だけでは断定が難しく、多くの場合、キャベツの茎葉が晴天の日中にも関わらずしおれてしまう状況や、他の株に比べて成長が著しく悪いなどの状況を見て、根こぶ病の感染を疑います。場合によっては、株全体が弱り枯死することもある病気です。
被害の進行と生育への影響
生育初期に感染した場合、定植後1カ月頃から下葉がしおれ、収穫には至りません。生育後期に感染した場合には、結球部が肥大せずに通常よりも小さく、収量の低下または収穫できるサイズにならないこともあります。
類似した根系障害との違い
根こぶ病と似た症状を引き起こす根系障害には、ネコブセンチュウによる被害があります。ネコブセンチュウのこぶは、こぶが小さく数珠状に連なって表面がザラついているのに対し、根こぶ病はこぶが大型でツヤがあるのが特徴(こぶ形成後間もなく日が浅いときは白色で滑らかな形状。一方、日がたつと褐変して滑らかな表面は粗くなる)です。
キャベツに根こぶ病が発生する原因
高温・多湿と酸性土壌が病気を助長
根こぶ病菌は、気温20〜25℃前後の高温多湿な環境で活発に活動し、酸性土壌(pH4.5~6程度)で特に発生しやすくなります。雨が多く水はけの悪い圃場や地下水位が高い圃場では発病が多くなります。
病原菌の土壌伝染メカニズムと休眠胞子の長期生存
根こぶ病菌は、こぶとなった根の細胞から放出された胞子が土中で休眠して年を越すため、この胞子がもとになって新たな感染を引き起こします。この休眠胞子は、長期間生存できるため(数年から10年以上にわたって土壌にとどまり、適した条件になると再び活性化する)、一度発生すると感染を繰り返します。
キャベツ根こぶ病の防除と対策のポイント
圃場の環境整備
排水性の悪い圃場では、病原菌が拡散しやすくなります。圃場の水はけをよくするために、高畝にしたり、暗渠(あんきょ)を設けてたりして排水を改善することが効果的です。また、石灰資材を施用して土壌のpHを6.5〜7.0に調整することで、病原菌の活動を抑えることができます。
生育初期の防除・予防的対策
根こぶ病は発生してからの対処が難しいため、定植前の土壌処理が重要です。発病リスクが高い圃場では、事前に薬剤を散布し、菌の密度を下げておくことが推奨されます。また、育苗段階で土壌消毒(セルトレーに灌注処理)を行うことで、本圃での消毒に比較して手間の掛からない対策も可能です。
キャベツ根こぶ病を防ぐための栽培管理のポイント
輪作の重要性と適切な作付け計画の立て方
アブラナ科作物を連作しないことが根こぶ病対策の基本です。輪作を行い、アブラナ科以外の作物を栽培することで病原菌の減少を促します。また、おとり作物(作付け前に、おとりとなるアブラナ科作物を植え付けて根こぶ病菌の休眠胞子を発芽させて、おとり作物に感染させて菌密度を下げる方法)も効果的です。また、抵抗性品種を導入することで、病害の発生を抑えながら安定した収穫を目指せます。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。