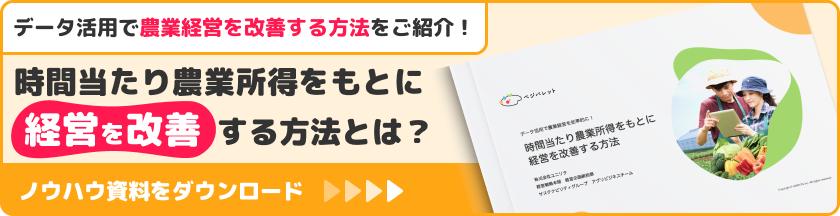キャベツの白さび病とは?原因・症状・防除対策を徹底解説
キャベツの「白さび病」は、栽培中の葉に白い斑点が現れて次々に広がる厄介な病気の一種です。
この記事では、キャベツの白さび病の症状・原因・発生しやすい条件について詳しく紹介します。
キャベツの白さび病とは?基本情報と病害の特徴
白さび病の病原菌と発生メカニズム
キャベツの白さび病は、糸状菌の一種であるAlbugo属菌によって発生する病害です。この病原菌は生きた宿主細胞から離れた状態では増殖できない絶対寄生菌ですが、圃場周辺の植物残渣や宿主となるアブラナ科作物の組織内に菌糸また卵胞子の状態で生存(越冬または越夏)して、生育適温になって胞子のうを形成し、胞子を飛散させて空気伝染します。葉に現れる白色の粉状物は、病原菌の胞子のうで、次々と感染を広げます。
白さび病にかかるとキャベツはどうなる?
葉裏に白色でいびつな小斑点を形成するのが感染の始まりです。やがて、斑点部分の葉の表皮が破れて粉状物(病原菌の胞子のう)を作り、胞子を飛散します。その後、病斑部分の葉は黄色っぽく退色し輪紋となります。
白さび病の症状と診断ポイント
他の病害との違い
白さび病は、黒斑病や、べと病と症状が似ていますが、以下のような違いがあります。
- 黒斑病:
主に外葉に黒褐色の同心円状の輪紋のある斑点が現れる。
病斑は破れやすく、乾燥して古くなると穴が開く。 - べと病:
下葉から発生して、葉脈の間に淡黄褐色の病斑を作る。
病斑の葉裏部分には、霜状のカビ(病原菌の菌糸)が見られる。
キャベツ白さび病の発生要因と感染経路
発生時期と気温・湿度
白さび病は、比較的気温の低い晩秋から早春の多湿な条件で多く発生します。
被害を拡大させる要因
密植環境では、風通しが悪くなって湿度が高くなり、白さび病の病原菌が繁殖しやすくなります。また、アブラナ科作物を連作することも多発する要因です。
キャベツ白さび病の効果的な防除対策
栽培管理でできる予防策
白さび病の発生を防ぐには、適切な株間を確保し、風通しをよくすることが大切です。また、畝を高くして排水性をよくすることで、過剰な湿気を防ぐことができます。マルチの使用は、土壌中の過剰な湿気の放散を防ぐことにもつながります。
適切な作付け計画と肥培管理
輪作を取り入れ、アブラナ科作物の連作を避けることで病原菌の密度を低下させ、発生の抑制が期待できます。また、窒素肥料を多用するような肥培管理では、軟弱な生育になって病気にかかりやすくなってしまいます。肥培管理にも注意が必要です。
感染拡大を防ぐ圃場の衛生管理
病原菌が残って次作に発生しないよう、収穫後の残渣を適切に処理することも重要です。
農薬による防除
予防散布
白さび病は冷涼な気温と多湿環境で繁殖するため、発生を抑えるには、予防的な薬剤散布が有効です。定期的に散布することで発生を抑えましょう。
まとめ
白さび病は、一度発生すると広がりやすい病害です。適切な排水対策・輪作・農薬の適正使用によって予防することが重要です。特に、早期発見と適切な対策を心がけることで、安定したキャベツ栽培を実現しましょう。持続可能な農業を実現するために、本記事で紹介した防除方法をぜひ活用してください。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。