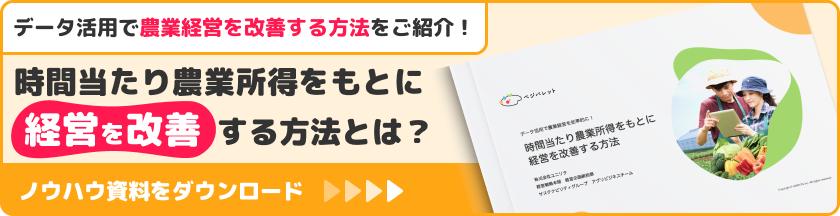ヨトウムシが白菜にもたらす被害とは?発生時期・防除対策を解説
白菜栽培において、ヨトウムシは収穫量と品質に大きな影響を与える害虫です。
この記事では、白菜に発生するヨトウムシ類の生態と被害、そして被害を防いで収穫量を守るための実践的な防除対策について、詳しくご紹介していきます。
白菜のヨトウムシ被害の全容
白菜に発生しやすいヨトウムシ類の種類と生態
ヨトウムシは、漢字で「夜盗虫」と書く通り、昼間は土の中や葉の裏などに隠れていて、夜間に活動するチョウ目ヤガ科のガの幼虫です。ヨトウムシ類は、多くの種類の存在が知られていますが、白菜に特に被害をもたらすとされるのは次の3種類です。
- ハスモンヨトウ
- シロイチモジヨトウ
- ヨトウガ
これらヨトウムシ類の被害は、成虫であるガが葉の裏側に卵を産み付けることから始まります。成虫の雌一頭が生涯に産卵する数は平均1,000粒(多い種類では~3,000粒程度)。産卵1回あたりでは、数十~数百粒の卵を産み落とします。卵からふ化したばかりの若齢幼虫は、集団で葉を食害し、成長するにつれて分散し食害が広範囲に及ぶようになります。
ヨトウムシ類が引き起こす白菜の品質低下と収穫減
ヨトウムシ類は、白菜の葉を食い荒らすことで、以下のような被害をもたらします。
葉の食害
若齢幼虫は葉の裏側に群生して葉肉を食害し、表皮だけを残してカスリ状にしてしまいます。中齢以降では、葉に不規則に穴をあけて食害しますが、多発時では葉脈だけを残して葉全体をボロボロにするため、白菜の商品価値が損なわれます。
結球内部への侵入
成長した幼虫は結球内部に侵入し、中心部から食害することがあります。
収穫減
食害がひどい場合には、白菜が成長できずに収穫まで至らない株もでてきます。被害を受けた株は、仮に収穫できたとしても品質が劣るため、市場での評価が低迷する要因になります。
早期発見するためのポイント
ヨトウムシ類の防除では、早期発見が重要ですが、ヨトウムシ類はその生態から早期の発見が難しい害虫です。ここでは、早期発見のポイントを整理します。
他の害虫の見分け方
ヨトウムシ類の若齢期に見られる「葉裏だけを食べて表皮を白くカスリ状に残す被害」は、コナガも同様です。しかし、コナガの場合は、必ず幼虫が1頭ずつ食害しており、ヨトウムシ類の場合は集団で食害します。また、若齢期を過ぎる頃には、ヨトウムシは点々と穴をあけて食害するため、アオムシ被害との混同を招きますが、アオムシは体色が緑色で、成長しても葉の上で生活するため、容易に見分けられます。
卵塊の確認
成虫は卵を必ず葉裏に産みつけるので葉の裏面に注意して見ましょう。また、ふ化間もない若齢幼虫のときの食痕(カスリ状の被害)に十分に留意して、圃場の見回りを実施しましょう。
ヨトウムシ類の防除対策
ヨトウムシ類の被害を防ぐには、物理的対策、生物的対策の他、栽培環境の管理による対策を組み合わせて対策するのが大切です。
防虫ネットによる隔離(物理的対策)
防虫ネットの設置は、成虫(ガ)が白菜の葉に卵を産み付けるのを防げます。目合い1mm以下の防虫ネットを使用することで、その侵入を防ぎやすくなります。
天敵の活用(生物的対策)
ヨトウムシ類を捕食する天敵を活用する方法もあります。ヨトウムシ類に卵を産み付けて、ふ化した幼虫がヨトウムシ類を捕食する寄生蜂もいます。こういった天敵生物を生かすためにも、過度な農薬散布(殺虫剤)を避けて最小限にとどめ、天敵生物が生き残りやすい環境にすることも大切です。
土壌管理と適切な耕作による予防(環境的対策)
ヨトウムシ類は土の中で蛹(さなぎ)になって過ごします。そのため、土を耕してさなぎを地表に出してやることで鳥や天敵に捕食させることが可能です。また、マルチング(黒マルチ・シルバーマルチ)を活用することで、成虫になってガとして飛散するのを防ぐことができます。
ヨトウムシ類の駆除方法
薬剤散布
ヨトウムシ類は老齢幼虫になると薬剤に対する抵抗性が増すため、若齢幼虫のうちに散布して駆除することが重要です。被害が目に見えるようになった段階では手遅れになることがあるため、発生予察に基づく早期の散布が求められます。ヨトウムシ類の発生予察については、フェロモントラップを利用して判断したり、地域によっては発生予察情報(各都道府県による)が発表されたりしているため、これらを活用しましょう。
物理的な駆除
ヨトウムシ類は、葉裏に卵を産み付ける習性があるため、小まめに見回りして早期に卵を発見して除去するのも有効です。また、ふ化間もない若齢幼虫が食害し始めた証(カスリ状になった葉)を見つけたら、幼虫の集団ごと葉を切り取って処分するのも効果的です。成長した個体が潜んでいる場合もあるため、卵が産み付けられた葉を探すのと同時に、葉裏に潜む幼虫を見つけて捕殺しましょう。
まとめ
白菜栽培においてヨトウムシ類は深刻な被害をもたらす害虫ですが、早期発見と適切な防除策を行うことで最小限の被害に抑えることが可能です。一方、被害が大きくなると、薬剤散布による防除の手間や経費が余計にかかったり、収穫時の調整作業の工数が増加したりするなど、予想しないコストが上乗せになるばかりか、取引価格(ひいては売り上げ)にも影響します。本記事が、白菜栽培の対策を考えるきっかけとなり、持続可能で安定した農業経営の実現につながることを願っております。
執筆者情報

株式会社ユニリタ
アグリビジネスチーム
ユニリタのアグリビジネスチームのメンバーが執筆しています。
日々、さまざまな農家さまにお会いしてお聞きするお悩みを解決するべく、農業におけるデータ活用のノウハウや「ベジパレット」の活用法、千葉県に保有している「UNIRITAみらいファーム」での農作業の様子をお伝えしていきます。